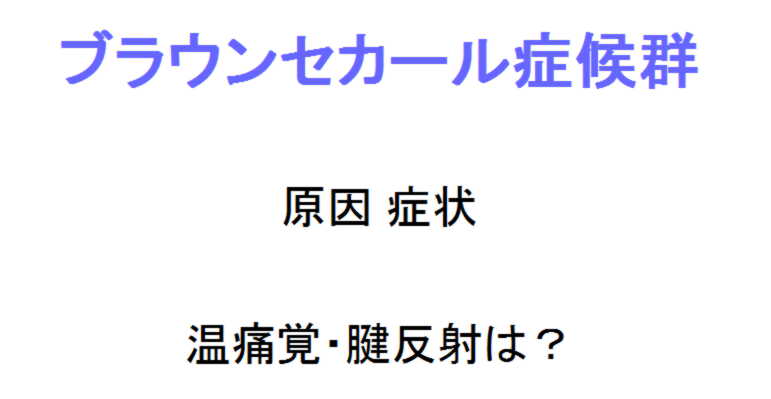ブラウン・セカール症候群は、国家試験にも頻繁にとりあげられる症候群です。
なぜ、これがよく問題に出されるのでしょうか?
それは、この症候群の発生メカニズムと症状の関係が神経学的に理路整然となっており
神経学や解剖学の複合的な理解を要する問題をつくれるからです。
ブラウンセカール症候群とは?
脊髄半側症候群とも言われます。
ブラウンせカール症候群は、脊髄の半側(右側または左側)の障害です!
原因
片側の脊髄腫瘍、外傷、脊髄への血行障害、多発性硬化症(MS)などがあります!
純粋なブラウンせカール症候群は、特殊な外傷で脊髄が片側だけ損傷する場合に生じます。
脊髄の伝導路について
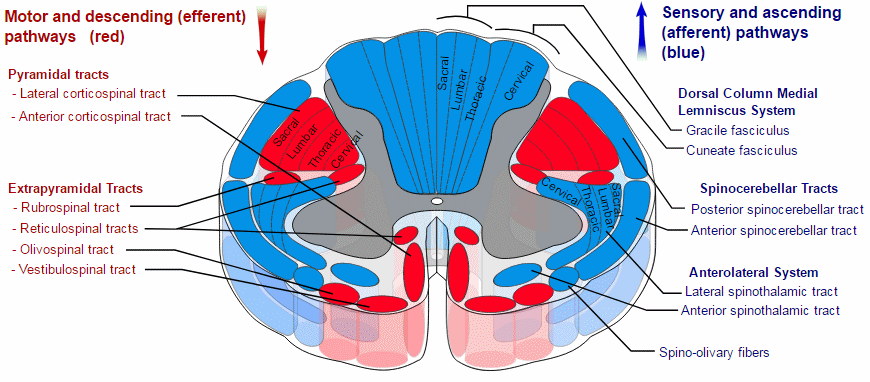
Wikipediaより
図の説明
図の赤色の部分は、下行性の神経線維で、青色の部分は上行性の神経線維の通る部分です。
図では、見やすいように、左側に下行性神経抜群の名称、右側に上行性神経線維の名称を記載してあります。
図でも分かるように、脊髄には上行性と下行性の神経線維が通っています。
図の向かって右側(青色の上行性神経線維の説明がある側)の神経線維は、脊髄の、その部分より下からの情報が含まれています。
さらに、温度覚や痛覚(温痛覚)は、脊髄の中に入ってくると、反対側に交叉して上行するため
反対側からの情報が含まれることになります。
症状
例えば、右側の胸髄が障害された場合
温度覚・痛覚(温痛覚)は?
伝導路で言うと、脊髄視床路の障害になります!
右側の脊髄部分をずーと上がってきた上行性の神経線維(温度覚、痛覚)が、その部分でストップします。
ストップした温痛覚の神経線維は、元々は左側から脊髄に入って、交叉して上がってきたものです。
そのため、その障害部位よりも下で反対側からの情報がストップすることになります。
繰り返しになりますが、この場合、反対側(左側)の温度や痛覚が分からなくなります。
深部感覚は?
伝導路で言うと、後索路です!
深部感覚は脊髄レベルでは交叉せずに同側を上行する神経線維です。
そのため、温痛覚とは異なり、障害部位以下で同側からの深部感覚の情報がストップすることになります。
運動線維(下行性神経線維)は?
伝導路で言うと錐体路(外側皮質脊髄路)です!
下行性の神経線維(運動神経)は、
大脳皮質の運動野(4野、6野)からスタートして下行し、
延髄の下部で大部分の線維が錐体交叉して反対側を下行します!
そして、脊髄の前角細胞のところでシナプスを介して
目的の筋へ向かいます!
そのため、ブラウンせカール症候群のように
下部延髄よりも下にある脊髄の片側が障害された場合、
障害部位より下の同側の筋は、痙性麻痺を起こします!
そして、障害部位は、同側の筋が弛緩性麻痺を起こします!
これは、障害部位では、筋に命令を送る神経である前角細胞自体が損傷されるためです。
反射については、以下の記事に詳しく書いていますので参考にしてください!
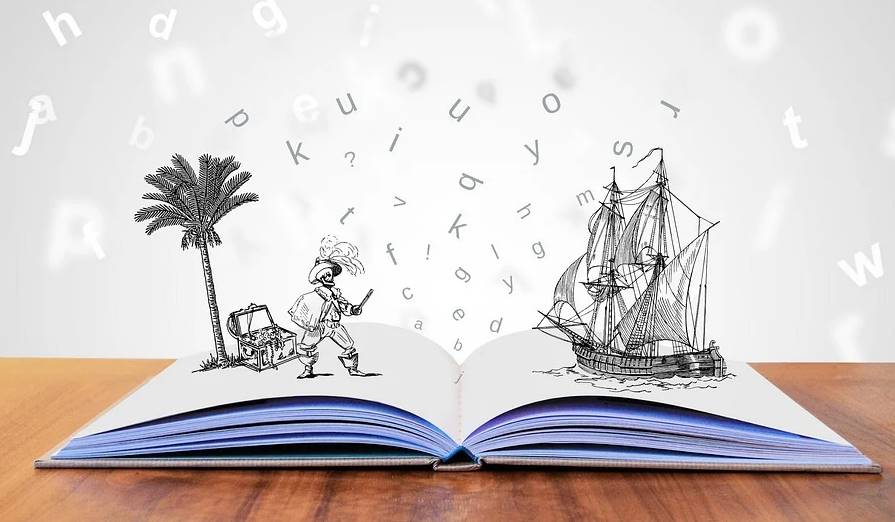
症状(まとめ)
感覚障害
・障害部位以下の反対の温痛覚の感覚麻痺
・障害部位以下の同側の深部感覚、触覚の麻痺
※触圧覚は、前脊髄視床路と後索で補っているため障害部位レベルでは完全な感覚脱失にはなりません。
運動麻痺
・障害部位で、同側の弛緩性麻痺
・障害部位より下で、同側の痙性麻痺
参考:新病態生理できった内科学(医学教育出版社)、集中講義生理学(メジカルビュー)、ウィキペディア、Wikipedia